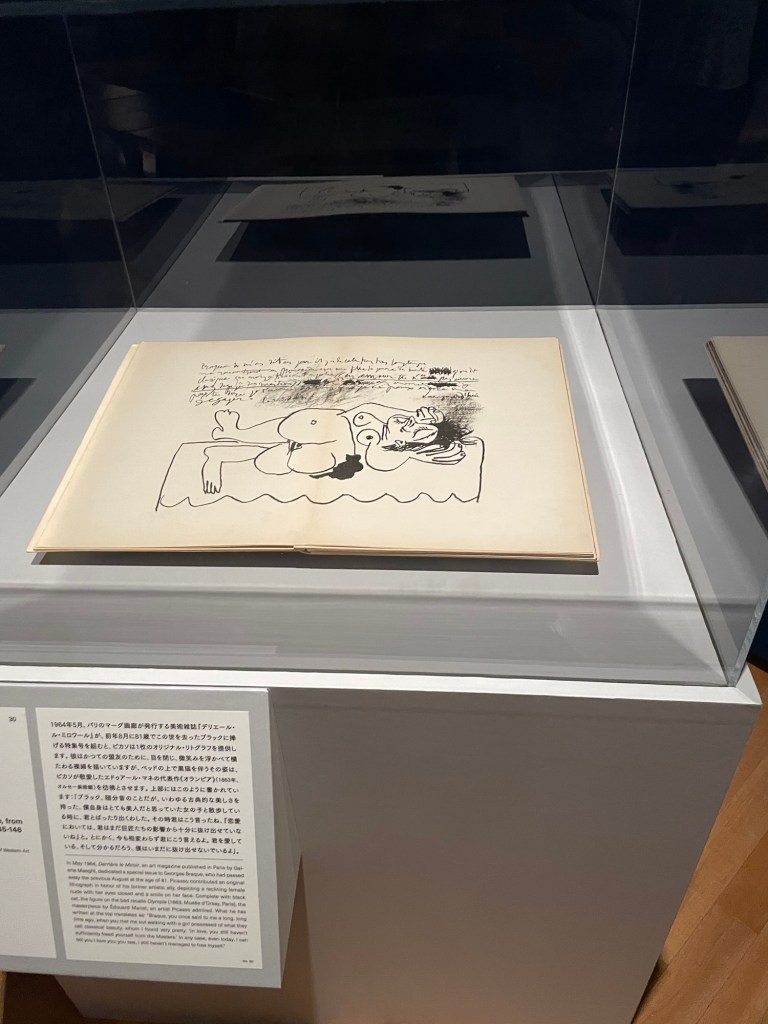九段ハウスを出ると濃いブルーの空の下にいた。風は無く空気は冷たかった。少し歩くと靖国神社の大きな鳥居とそこから緩やかな傾斜を伴い真っ直ぐに伸びる石畳が見える。靖国通りを跨ぐ歩道橋を使い反対側の歩道へ行く。千鳥ヶ淵は陽の光を写していた。

九段ハウスでは「キュレーションフェア」なるアートフェアが開催されており、近代以降の日本における美術のあり方を示すものだった。また第二次世界大戦以前、以降の日本を現在の東京で鑑賞する効用を九段下という地はより大きなものとしていたと思う。九段ハウスと呼ばれる建物は関東大震災を経た東京で耐震構造のパイオニアである内藤多仲によって主に設計された旧私邸である。
大きく3部に分かれる展示の一つは李朝陶磁によってそのほとんどが占められていた。柳宗悦が発見したとされる李朝陶磁の「下手物」の美は「民藝」という捉え所の難しい理念によって現代日本の大衆にまで浸透している。しかしながら柳の視点の当時的な難しさは少なくない人達によって批判されており、まさにその点を指摘しつつ多くの李朝陶磁をこの場で展示したキュレーションは素晴らしいと思う。
つまり日本による朝鮮への政治的、文化的支配を基に論理立てされた「民藝」はオリエンタリズム、立場の弱い者へのハンパな共感であるという批判に正面から向き合うべきであり、関東大震災を経て建築された耐震構造に優れた財界人の私邸において朝鮮の陶磁器を鑑賞する俺達は、当然震災時に日本人が醜い大衆心理によって多くの朝鮮人を殺した事実の前に立たされる。おそらくそうあるべきだった。
もちろんキャプションはここまで直接的な言い方をしていないし、このような強い言葉はとかく感情的な素人の戯言に過ぎないのかもしれないが、アンミカの「白って200色あんねん」に大いにインスパイアされたというキュレーターの言葉はギャグを超え、大阪に生きた、あるいは今も日本に生きる在日コリアンの存在を射程の内に置いている。社会的差別を俺たちは乗り越えていないことは、現在の政治的状況を見るに明らかだろう。殆ど自然光のみで見る白磁の壺は別に美しくなかった。

九段ハウスを出て、気持ちは穏やかだった。前向きな仕事に立ち会ったからだったと思う。時間はまだ14時を回った頃だったと思うが、特に予定が無いため自宅のある築地に向かって歩いていた。皇居周辺は虚無であり、実際の生活から程遠く感じる。堀の側に小さな水仙が咲いていて可愛かった。水面には水鳥が微睡み、その下で褐色の鯉が重たく泳いでいる。一ツ橋の工事現場ではアフリカ系の作業員がトラックの駐車を補助し、それはとても自然に風景に馴染んでいた。